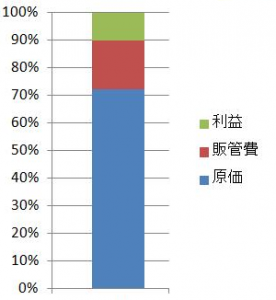石油ファンヒーターの国内シェア
下の図は、家庭用石油ファンヒーターの国内シェアを予想したものです。

ダイニチ工業がシェアの半分50%を握り、コロナが25%、トヨトミが14%、アラジンが10%と予想します。予想の理由を以下に示します。
ぶっちぎりのシェア1位、ダイニチ工業
ダイニチ工業が石油ファンヒーターのシェア1位であることは間違いありません。なにしろ、ダイニチ工業自ら、2009年から、4年連続シェア1位を達成した、といっています。また、新入社員向けのページにてシェアは50%ともいっています。
株主通信にあるように、ダイニチの売上の7割を石油ファンヒーターが占めているようです。ダイニチの2013年3月期の売上高は232億円。ですので、石油ファンヒーターの売上高は162億円です。石油暖房の売上高168億円にちゃんとおさまっています。
2012年度の家庭用石油ファンヒーターの出荷額は376億円ですので、ダイニチの石油ファンヒーターがすべて家庭用とすると、金額ベースのシェアは42%になります。
ダイニチ工業は、市場調査会社GfK Japanによる、全国有力家電販売店の販売実績集計で、メーカー別数量、金額シェアともにシェア1位といっています。ですので、新入社員向けのページでいっているシェア50%は、金額ベースではないことになります。42%をシェア50%とは言えません。
ということで、新入社員向けのページでいっているシェアは50%とは、メーカー別数量、すなわち出荷台数のことを指します。2012年度の家庭用石油ファンヒーターの出荷台数は285万台です。ですから、ダイニチの石油ファンヒーターの出荷台数は143万台になります。
ダイニチは、低価格の石油ファンヒーターのシェアを高めてきました。出荷台数シェア(50%)の存在感に比べて金額ベースシェア(42%)の存在感が小さくなるのは当然です。2012年度の家庭用石油ファンヒーターの1台あたりの平均出荷金額は13,192円です。ダイニチの1台あたりの平均出荷金額は11,328円です。やはり、ダイニチは、他のメーカーよりも低価格な石油ファンヒーターを売っているようです。
| ダイニチの売上高 |
232億円 |
| 石油ファンヒーターの売上高 |
162億円(シェア42%) |
| 石油ファンヒーター出荷台数 |
143万台?(シェア50%) |
| 1台あたりの平均出荷金額 |
11,328円? |
トータル暖房のコロナ
コロナの石油ファンヒーターのシェアはよく分かりません。東証1部上場企業とはいえ、公開資料が少ないためです。むしろ、同じ東証1部上場企業のダイニチ工業の透明性の方が際立ちます。
コロナは暖房機器全体のシェア1位だといっています。ですが、石油ファンヒーターのシェアはそれほど高くないようです。
平成14年の越後ジャーナルの記事では、石油ファンヒーターのコロナのシェアは30%でトップと書かれています。その年以降は、30%を行ったり来たりの状況ではないかと推測します。
ダイニチとコロナの本社は、新潟県にあります。新潟県の石油ファンヒーターのシェアが分かれば、突破口になるはずです。ありました。経済産業省の子ども向けのサイトです。石油ストーブのシェアが74%とあります。
しかし、なんだか古い統計のようです。もっと探してみると、NPO法人住民安全ネットワークジャパンの記事がありました。新潟県は石油ファンヒーターの国内シェア9割、ということです。2013年1月の記事です。
この記事を信頼すれば、ダイニチのシェアは5割なので、コロナのシェアは4割ということになります。NPO法人住民安全ネットワークジャパンは新潟県人が集まった組織のようで、会員に櫻井良子氏もいます。どこから得た情報なのでしょうか?独自の情報なのでしょうか?新潟県の統計に、それらしい情報が見当たらないので。おそらく石油ストーブ全体と間違えたのではないかと思います。
というわけで、本サイトでは、コロナの石油ファンヒーターのシェアは20~30%ぐらいではないか、と推測します。
トヨトミ
トヨトミの売上高は、平成25年3月期の実績で160億円です。そのうち、どれだけが石油ファンヒーターの売上高なのでしょうか?
トヨトミも、石油ファンヒーターを日本国内で生産しているようです。自社工場は2カ所。本社工場は、名古屋にあり、額田工場は、岡崎市にあります。
幸運にも、それぞれの工場で生産しているものが違うことが分かりました。すなわち、本社工場では、石油ストーブを、額田工場では、石油ファンヒーターを生産しています。
額田工場がある岡崎市の統計をしらべてみました。工業関係の統計に、「町別事業所数、従業者数、製造品出荷額」がありました。額田工場の住所は、樫山町です。ありました。2010年の統計です。事業所数5、従業者数475人、製造品出荷額115億円。
トヨトミ以外の工場の出荷額も含まれているので、製造品出荷額115億円を事業所数5で割ります。すると23億円。トヨトミの額田工場の従業員数は、約145人です。岡崎市の「従業者1人当たりの製造品出荷額等・付加価値額」という統計で、従業員100~199人の工場が生み出す「1事業所当たりの製造品出荷額」は26億円ですので、だいたいあっていると思います。
トヨトミ額田工場の出荷額は23億円。ここでは、石油ファンヒーターと石油給湯機をつくっています。トヨトミの石油給湯器の出荷額は分かりません。ですから、ここからは推測になりますが、トヨトミの石油ファンヒーターの売上高は20億円ぐらいではないでしょうか。
2010年度の石油ファンヒーターの出荷額は366億円です。ですから、トヨトミのシェアは金額ベースで5%になります。
想定よりも、シェアが小さいです。もしかしたら、本社工場でも石油ファンヒーターをつくっているのかもしれません。あるいは、額田工場の生産性はもっと高く、出荷額はもっと大きいものなのかもしれません。
なにしろ、トヨトミの石油ファンヒーターのラインナップは11機種もあり、機種の数がシェアに比例している可能性があるためです。
トヨトミは海外での販売が大きい会社です。全体売り上げのうち、国内の売上は7割、海外の売上は3割のようです。だとすると、国内売上は112億です。トヨトミの主力商品は石油ストーブなので、石油ファンヒーターは国内売上の50%以下になります。
主力商品が売り上げトップになるはずだからです。ですから、トヨトミの国内の石油ファンヒーターの売上は56億以下になります。
2012年度の家庭用石油ファンヒーターの出荷額376億円のうち、トヨトミの売上は56億円。つまり、トヨトミのシェアは15%を超えない、ということになります。
アラジン
アラジンのファンヒーターの売上を調べるために、輸入販売会社日本エー・アイ・シーの売上を探しましたが、分かりませんでした。さらに親会社の千石の売上高もしらべたのですが、非上場企業のため、公表していないようです。(後に調べたところ、2012年の実績で売上高177億円)
経済産業省の製品安全ガイドにリコール情報があり、アラジンの製品の対象台数が載っていました。情報が少ないため、出すだけで他意はありません。
さて、そこに何と書かれているかというと、「AKF-P321N」という機種が、2010年8月から2011年2月4日までの半年間に、対象台数151,182台が出荷されている、ということでした。
2010年度の国内出荷台数は、288万台です。この1機種だけでも国内の5%くらいシェアがあるといえます。アラジンは、他にも石油ファンヒーターを販売しているので、10%はシェアを確保しているのではないか、と推測します。
千石の2011年度の実績では、石油ファンヒーターを30万台製造しているとのことです。2011年度の国内販売台数は309万台ですので、シェア10%です。